Kuttner腫瘍とは、1896年にKuttnerにより初めて報告された炎症機転による疾患で、慢性硬化性唾液腺炎とも呼ばれる。病理組織学的には、腺組織の萎縮・消失、線維の増生および線維内に散在する巣状の炎症性細胞浸潤がみられる。原因は、唾液腺の排泄管からの上行性感染に由来する慢性炎症、唾石に由来する排泄障害を原因とする慢性炎症、あるいはIgG4関連疾患に由来すると報告されている。顎下腺に好発し、耳下腺、舌下腺にみられることは稀である。 唾石の存在による場合には、一般に軽度の圧痛や自発痛を伴う。しかし、通常、疼痛症状はほとんどなく、硬い腫瘍性の唾液腺として触れ、一般的には片側性である。炎症が被膜を越えて周囲組織に達していると、可動性が失われている場合もある。治療は、炎症の急性期には消炎治療を施し、原因となる唾石が存在すればそれを除去する。しかし、唾石があっても多くの場合に腺体内であること、また、すでに罹患唾液腺は著しく硬化しており、唾液腺機能が認められないこと、多くの症例において異物感が強いことなどの理由で、唾液腺の摘出が行われる。ただし、自己免疫疾患由来の場合には全身精査を勧め、病態によっては経過観察かステロイド治療を行うこともある。
処置および経過
全身麻酔下にて顎下腺摘出術を施行した(図❹)。摘出した顎下腺は硬化しており、薄い皮膜で覆われていた。割面では分葉構造が不明瞭で、線維化していた(図❺)。術後に左側下顎下縁の知覚異常が認められたが、術後3ヵ月経過時には、自他覚的に症状はなく経過良好である。
病理組織学的検査所見
腺房細胞は萎縮ないしは消失しており、リンパ濾胞構造が散見された。リンパ球や形質細胞などの、炎症性細胞浸潤を伴う線維性組織も認められた(図❻)。
免疫組織学的検査所見
IgG4陽性の形質細胞が、組織全体に多数認められた(図❼)。
また、原因不明の出血をみたら、必ず出血性素因についても疑う。 図❸は以前勤務していた病院で、頬粘膜の血腫を主訴に受診された成人女性である。咬傷と思われたが、前腕にも出血斑(図❹)を認め、精査後に特発性血小板減少性紫斑病の診断を得た。
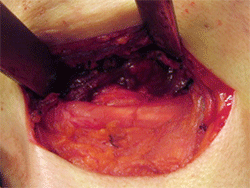
図❹ 術中写真
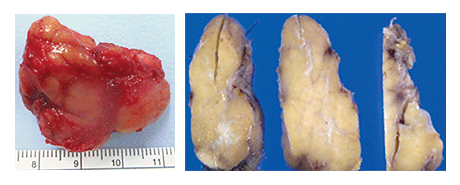
図❺ 摘出した顎下腺
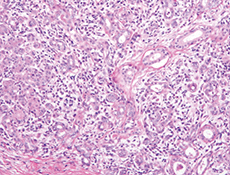
図❻ H・E染色 (x400)
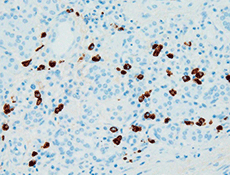
図❼ lgG4 染色 (x400)
![歯科医療従事者のための専門メディア : Dental Diamond[デンタルダイヤモンド]](https://dental-diamond.jp/pages/wp-content/uploads/2022/05/cropped-名称未設定d.png)
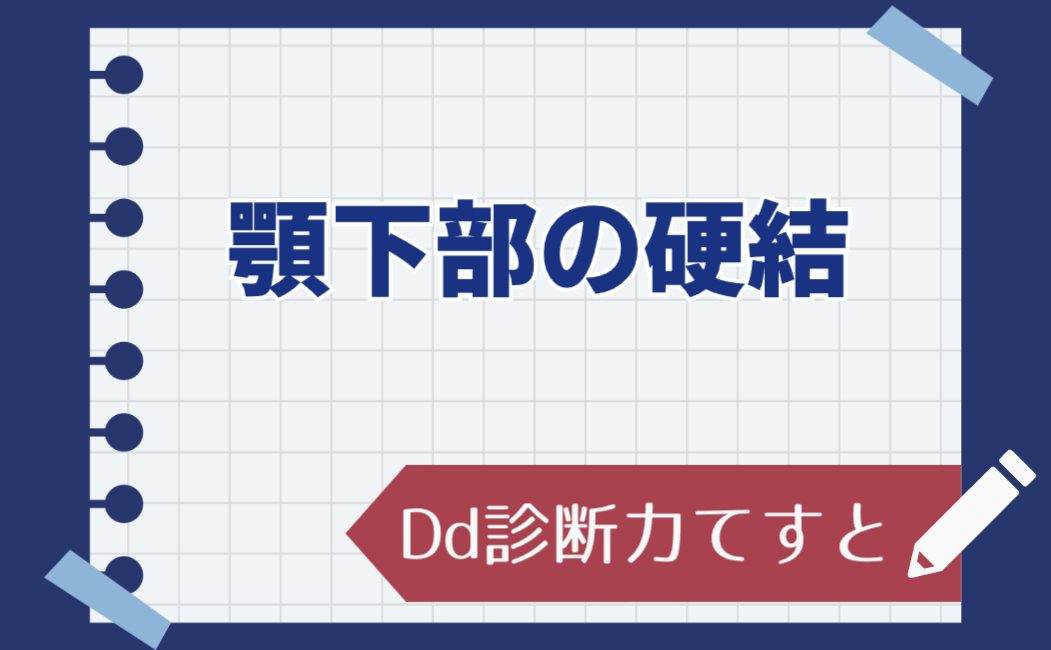
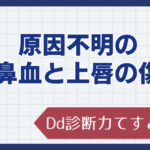
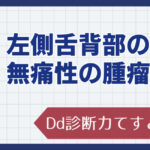
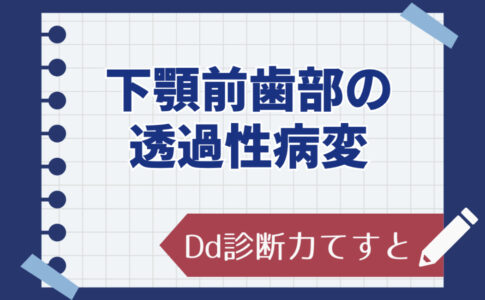
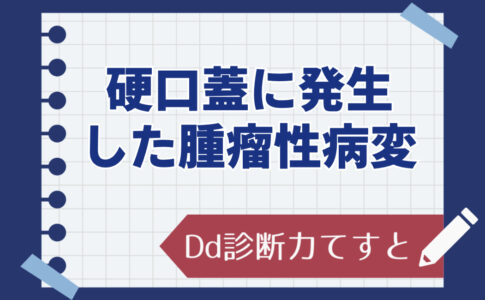

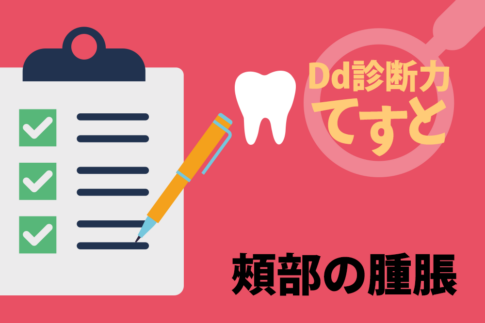
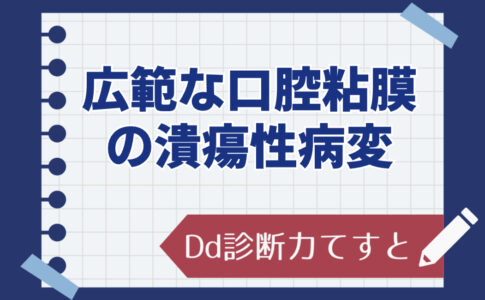

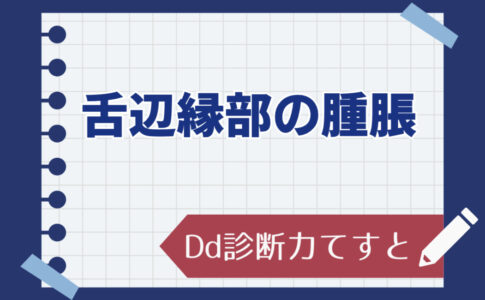
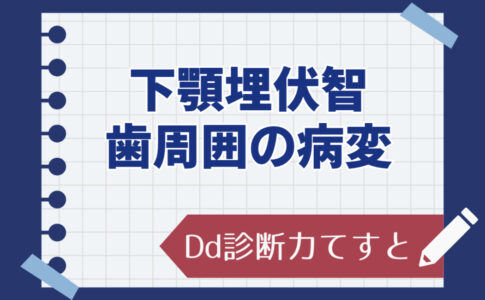



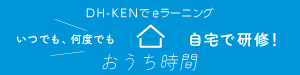
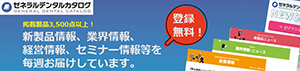


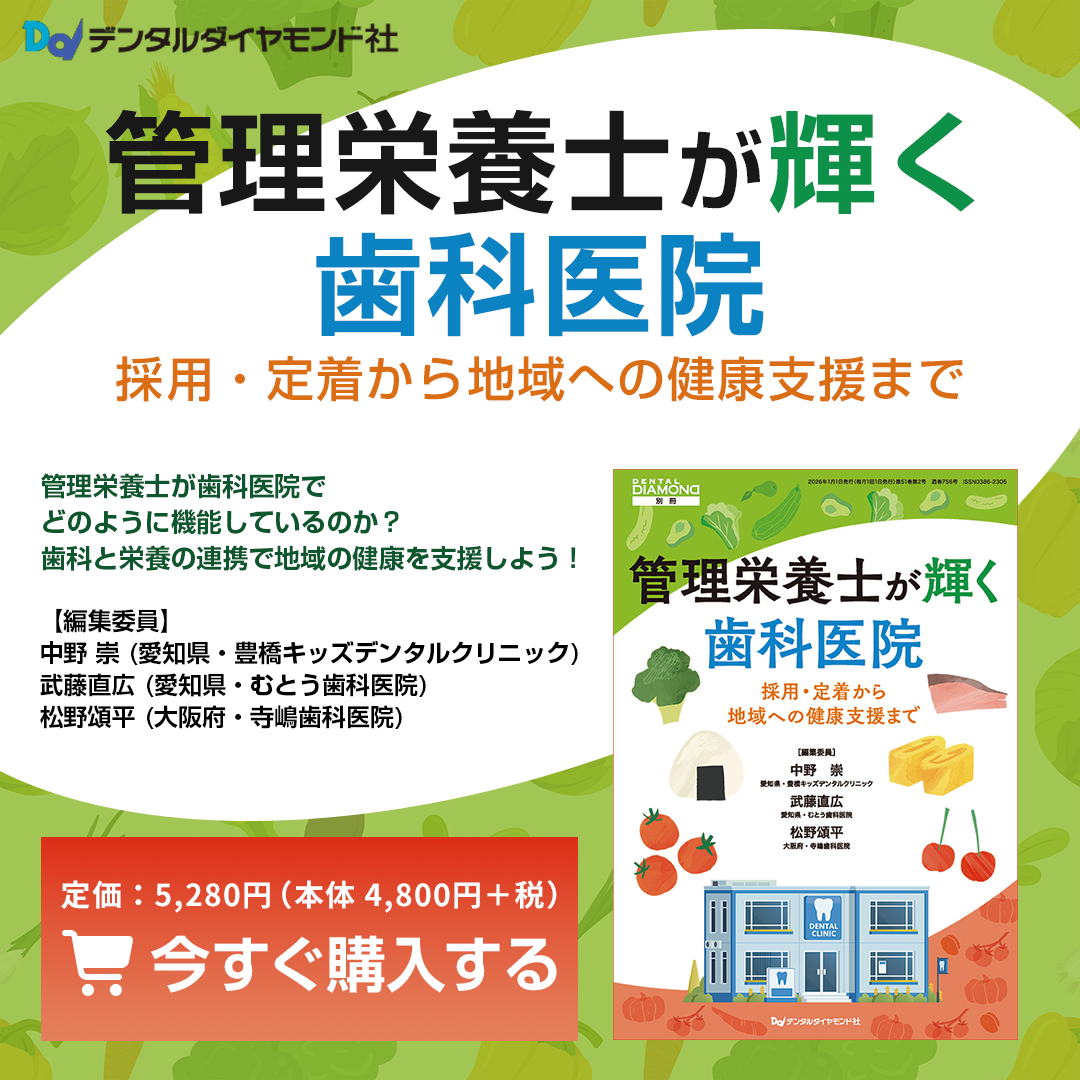
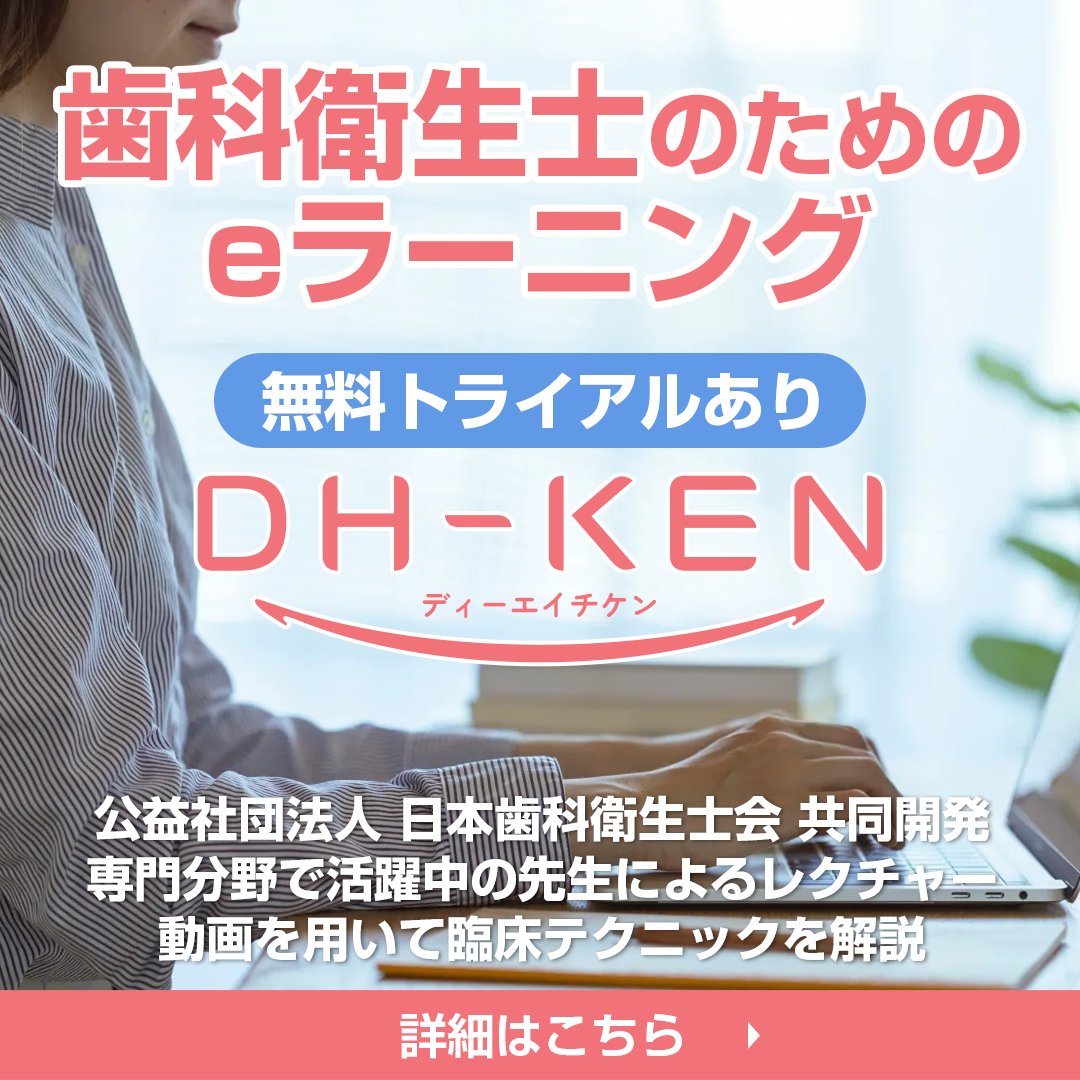

3.Küttner腫瘍