- 今後は女性にかぎらず、男性スタッフの育休取得も検討しなければならないと思っています。当院の男性スタッフは、歯科医師、歯科技工士の他、事務関係を担うスタッフなど複数名在籍していますが、今後、育休についてどのように考えればよいでしょうか。 東京都・I 歯科クリニック
-
1.育休の現状
一般的に「育休」とは、「育児・介護休業法」に基づく育児休業制度です。原則、1歳未満の子どもを養育するための休業で、男女を問わず利用でき、また、職場の就業規則に育児休業に関する規定や記載がなくても取得できる休業です。
したがって、スタッフからの申し出があれば、職場は休業の取得を拒めませんし、今後、育休を希望する男性スタッフは増えてくると思われます。
近年は、育児休業制度の認知度が上がったことや、企業による男性の育児休業取得率の公表などが進んできたことから、男性スタッフの育休取得率は、令和元年度:7.48%、令和2年度:12.65%、令和3年度:13.97%、令和4年度:17.13%と推移し、最新データの令和5年度には30.1%へと、大きく上昇しています。
しかし、女性の取得率が例年80%台半ばで推移している状況からすると、まだまだ低い比率です。育休の取得期間についても、女性は9割以上が6ヵ月以上取得している一方、男性は3ヵ月未満までが8割強を占める状況ですので、育休制度は男性スタッフに浸透しているとはまだ言い難いでしょう。
2.育休の今後
厚生労働省が全国の18〜25歳の男女、高校生・大学生などの若年層に対して行った育休取得に対する意識調査によると、男性・女性ともに9割以上は育休制度について認知しており、男性の39.4%が「育休を取得したい」、44.9%が「どちらかというと取得したい」と回答しています。
一方、現在、男性スタッフが育休を利用しなかった理由の1つとして、「収入を減らしたくなかったから」があります。育児休業を取得すると、職場からの賃金がなくなる一方、育児休業給付金を申請して受け取ることになりますが、休業開始時賃金日額(育児休業開始前、直近6ヵ月間に支払われた賃金の総額を180で割った額)×支給日数×67%が支給されることになるため、およそ現在の賃金の7割弱に収入が減ることになります。
支給上限額も設定され、日額上限15,690円、30日の支給日数の場合は支給上限額が315,369円となります。したがって、月額約47万円以上の賃金を得ているスタッフは、給付率が67%からさらに下がることになるため、比較的給与の高い男性スタッフの育休取得の障壁になっているといえるでしょう。 なお、令和7年4月からは、一定の要件を満たせば13%を上乗せし、67%と合わせて80%、つまり手取り額として考えた場合は10割相当になるような給付率となりますが、歯科医院では給与水準の高い歯科医師は、収入の面だけをみればデメリットとなる面があるのは確かです。
しかし、いまでは若年層の約8割弱は仕事(キャリア)とプライベートの両立を意識した価値観をもっているとされます。また、職場での育休の取得状況は、男性でも約6割を超える割合で「職場を選ぶ際に影響がある」と答えています。なお、育休の取得を推進させる制度として、女性の産後休業にあたる産後8週間のうち、4週間以内の期間を休業取得できる「産後パパ育休」の制度も始まりました。◉
歯科にかぎらず、多くの産業において人材不足が大きな問題となっていますが、歯科医院においても、社会保険の完備や有給の取得促進から、今後はさらに育休制度への対応、さらには男性スタッフに対する育休取得に向けた準備が必要です。
労働環境の整備状況が、今後の人材確保に影響を与えることは間違いないでしょう。【参考文献】 1)厚生労働省:令和5年度育児休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について.
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/assets/pdf/event/report_R5_2.pdf
門田 亮
デンタル・マネジメント・コンサルティング
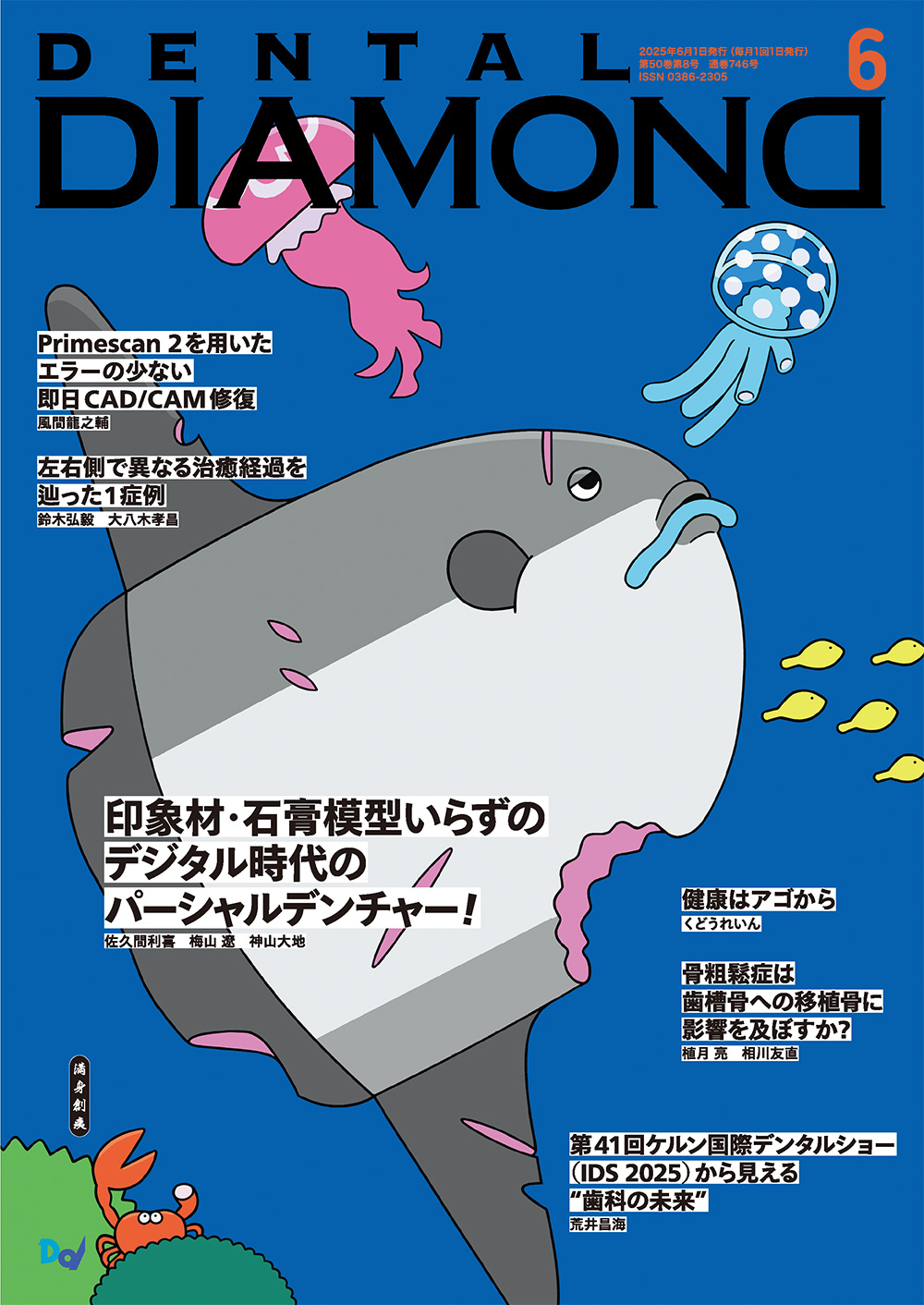
▽月刊デンタルダイヤモンドのバックナンバーはこちら▽
https://www.dental-diamond.co.jp/list/103
▽Q&Aのバックナンバーはこちら▽
https://dental-diamond.jp/qanda.html
![歯科医療従事者のための専門メディア : Dental Diamond[デンタルダイヤモンド]](https://dental-diamond.jp/pages/wp-content/uploads/2022/05/cropped-名称未設定d.png)
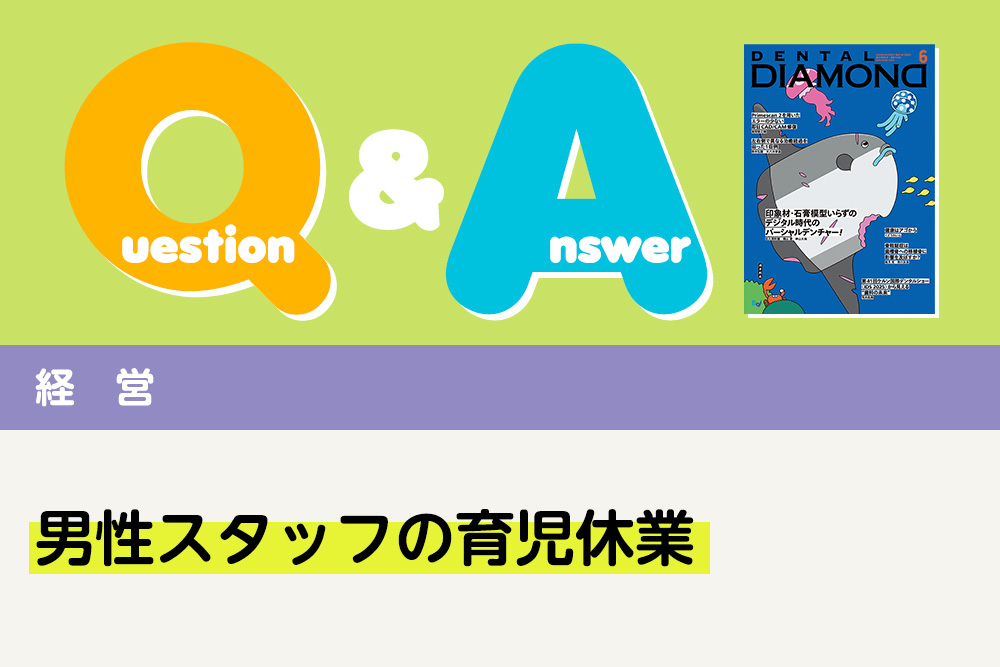
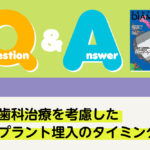

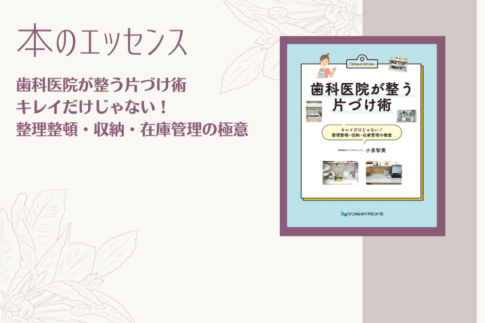
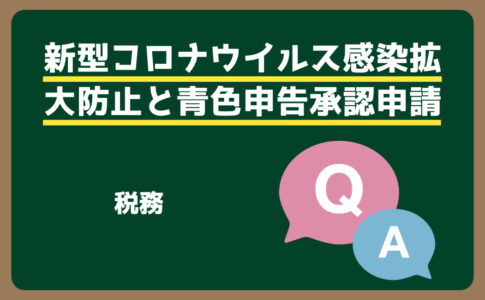
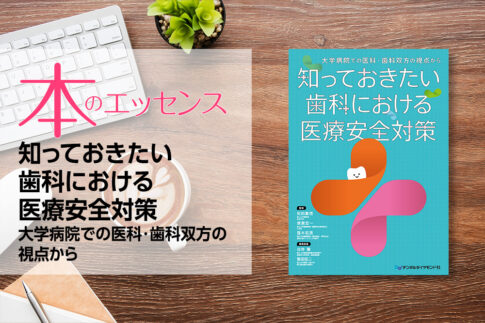
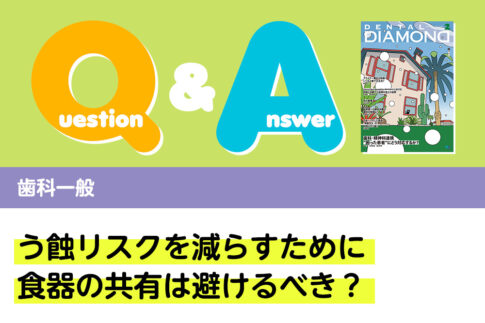
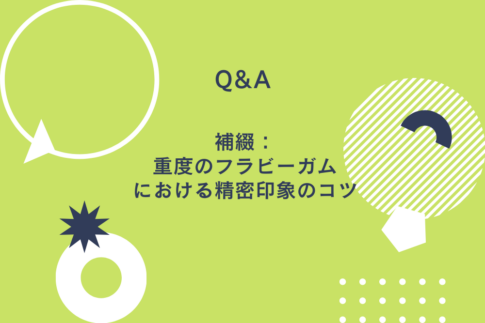
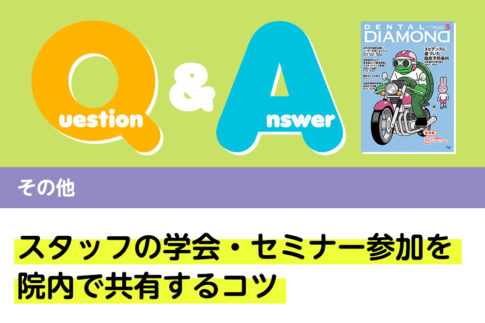
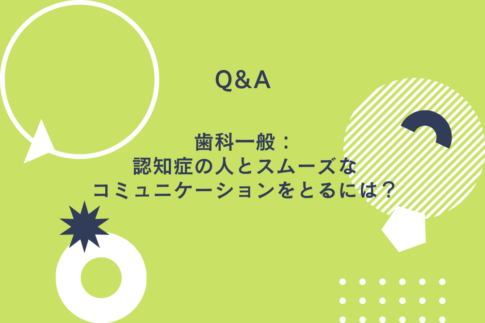




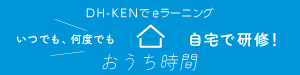
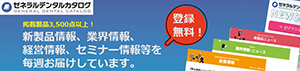


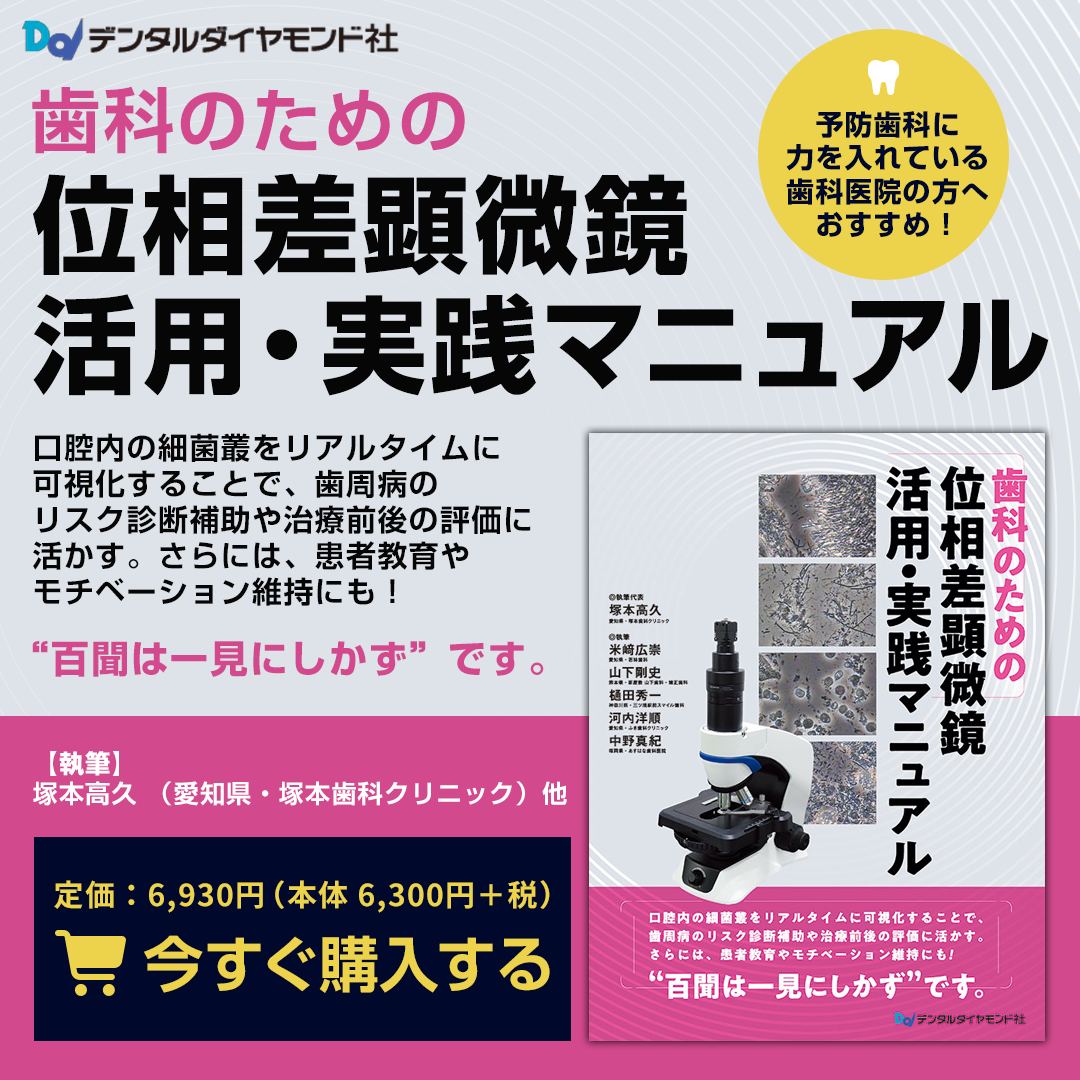
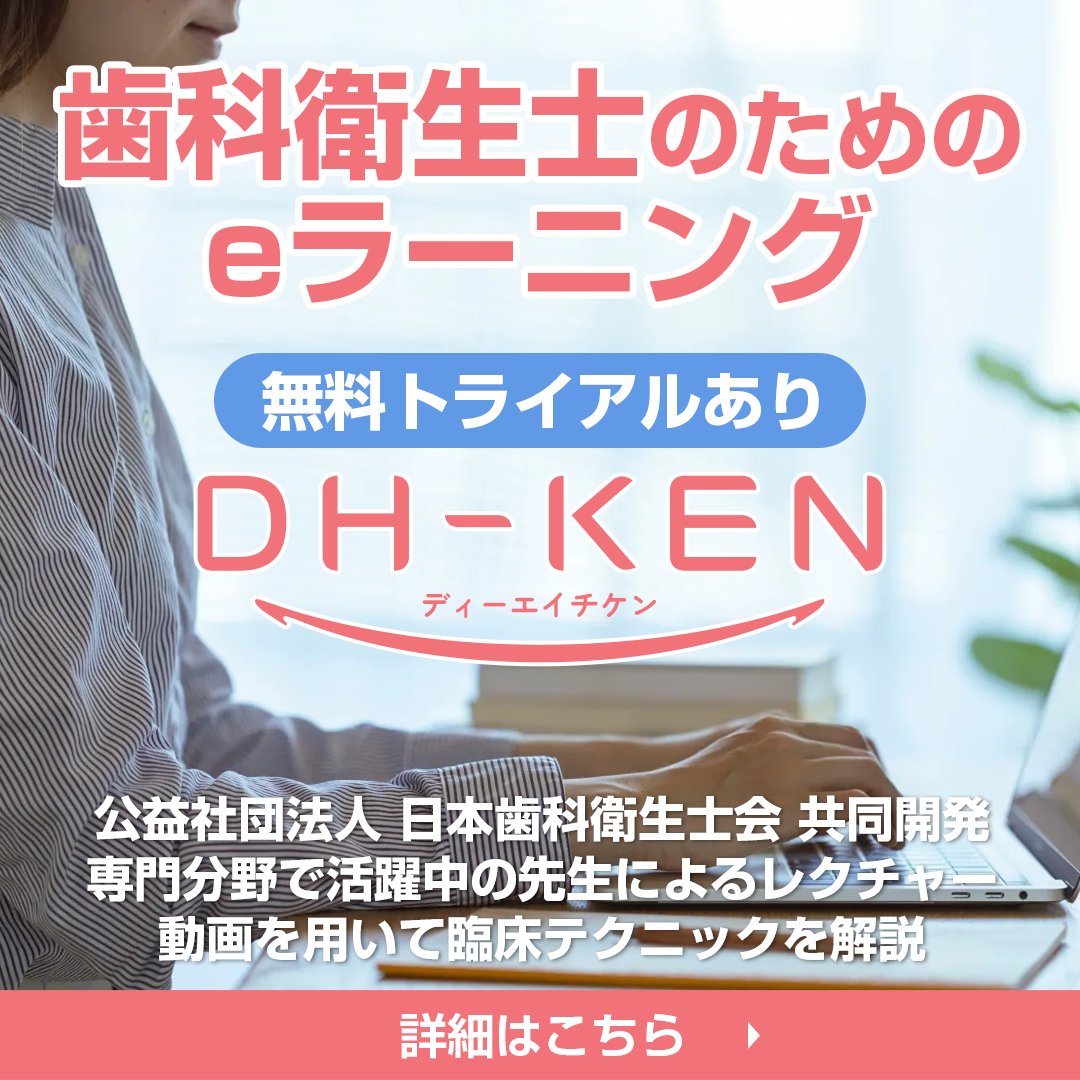

学術・経営・税務・法律など歯科医院での治療・経営に役立つQ&Aをご紹介いたします。今回は、月刊 デンタルダイヤモンド 2025年6 月号より「男性スタッフの育児休業」についてです。