放線菌は、口腔内常在菌叢を構成する通性嫌気性菌の1つであり、Actinomyces israelii が最も多いとされている。そして放線菌症は、頸部や顔面が好発部位であり、それらは、歯性感染症が主である。
臨床症状は、下顎角部や咬筋付近に紫色の硬く平たい腫脹(板状硬結)がまず現れ、開口障害、多発性膿瘍などが特徴といわれている。膿瘍形成例では、自潰、あるいは切開にて膿汁内に菌塊である黄白色の数mmの顆粒(Druse:ドルーゼ)を多数認める(図❸)。
本症例の診断は、典型的な臨床症状に加えて、膿汁中に菌塊を証明するか、培養による放線菌の証明、あるいは組織片から病理組織学的に菌塊を証明することである。本症例の顕微鏡下では、中心部にグラム陽性の分枝した顆粒状の菌糸が多数存在し、周辺部にはエオジン好性の棍棒体が放射状に配列していた(図❹)。
今日では、早期の抗菌薬の使用やステロイド薬、免疫抑制薬の使用により、典型症例が少なくなっており、診断に苦慮することが多い。組織片での病理組織学的な所見によって初めて診断される場合が多く、稀に軟組織に限局して発生することもある。
放線菌の病原性は単独では低いと考えられており、通常は他の細菌との混合感染か、あるいは宿主側の防御能の低下が発生に影響するといわれている。
本症例では、糖尿病などの基礎疾患があり、CTによる経時変化では、初診時において木村らが提唱している放線菌性顎骨骨髄炎像(平均5mm以下の小さな皮質骨吸収像)が認められ、ペニシリン系抗菌薬を主体とした治療法(倍量長期投与)と膿瘍切開などの外科的療法の施行により、骨シンチグラフィーによる異常集積の改善と軟組織自潰部の完全自然閉鎖を認めた(図❺❻)。

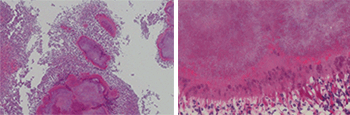
図❸ 膿瘍自潰部より排出した菌塊
図❹ 周辺部を棍棒体に縁取られた菌塊(左:弱拡大、右:強拡大)
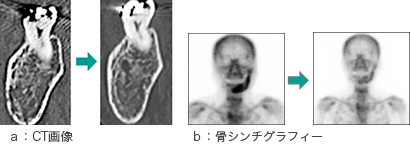

図❺ 放線菌性顎骨骨髄炎の改善
図❻ 半年経過後
![歯科医療従事者のための専門メディア : Dental Diamond[デンタルダイヤモンド]](https://dental-diamond.jp/pages/wp-content/uploads/2022/05/cropped-名称未設定d.png)




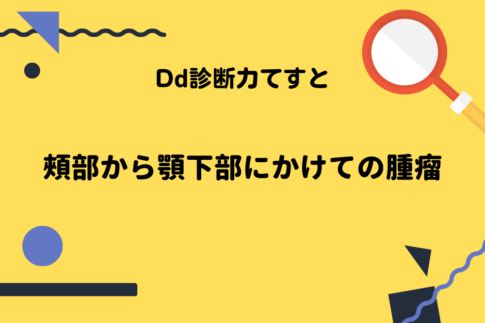
















1.顎放線菌症