- 院内の整理のため電子カルテを導入しようと考えています。電子カルテの保存期間や、その他、法的に注意が必要な事項があれば教えてください。 福岡県・N歯科クリニック
-
電子カルテは、法令上、電子保存の要件として「真正性」、「見読性」、「保存性」の確保が求められています。これらは、『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』(以下、医療情報安全管理ガイドライン)によれば、以下のとおりとされています。
・真正性「正当な権限において作成された記録に対し、虚偽入力、書き換え、消去およ
び混同が防止されており、かつ、第三者から見て作成の責任の所在が明確であること」
・見読性「電子記憶媒体に保存された内容を、『診療』、『患者への説明』、『監査』、『訴訟』等の要求に応じて、それぞれの目的に対し支障のない応答時間やスループット、操作方法で、肉眼で見読可能な状態にできること」
・保存性「保存性とは、記録された情報が法令等で定められた期間にわたって真正性を保ち、見読可能にできる状態で保存されること」
医療情報安全管理ガイドラインには、この3要件を確保するために必要な措置等が記載されています。もっとも、医療情報安全管理ガイドラインは、令和5年5月に公表された第6.0版から「概説編」、「経営管理編」、「企画管理編」、「システム運用編」に分かれています。そして、たとえば「システムがクラウドかオンプレミス」か、「運用責任担当者がいるかいないか」などで、参照すべき項目が異なります。
そのため、医療機関の実態に沿って医療情報安全管理ガイドラインを参照し、適切な措置を講じる必要があります。
電子カルテの保存期間は、紙カルテと同じ5年間です。カルテ以外の「療養の給付の担当に関する帳簿および書類その他の記録」の保存期間は3年間です。なお、カルテの保存期間の起算日は「完結の日」とされています。すなわち、各診療日からではなく、一連の診療が終了した日から保存期間のカウントが始まります。
ところで、病院ではなく診療所では、手書きまたはレセプトコンピュータ(レセコン)でカルテを作成していることが多いと思います。そして、レセコンで作成したカルテが「電子カルテ」と称されることもあります。しかし、電子カルテとして認められるためには、前述の3要件を満たすことなどが必要です。
一般に、レセコンで作成したカルテはこの要件を満たしませんので、正確にいえば「電子カルテ」ではありません。レセコンで作成したカルテはデータではなく、あくまでプリントアウトした紙媒体のものがカルテであり、紙カルテを5年間保存する必要があります。
なお、法令上の用語ではありませんが、データ自体がカルテとなる電子カルテと区別するため、レセコンで作成されたカルテを便宜上、「レセコンカルテ」と呼ぶこともあります。
最後に、患者からの医療過誤の主張に備えるため、損害賠償請求権の消滅時効を考慮し、カルテは最低10年間、保存することをお勧めします。
電子カルテであれば保存スペースの問題は生じませんが、紙カルテの場合はこの問題が生じます。法令上の保存期間である5年間を経過した後はPDF化し、紙カルテは廃棄するなどの方法をとれば、保存スペースの問題は多少は軽減するかと思われます。井上雅弘
銀座誠和法律事務所

▽月刊デンタルダイヤモンドのバックナンバーはこちら▽
https://www.dental-diamond.co.jp/list/103
▽Q&Aのバックナンバーはこちら▽
https://dental-diamond.jp/qanda.html
![歯科医療従事者のための専門メディア : Dental Diamond[デンタルダイヤモンド]](https://dental-diamond.jp/pages/wp-content/uploads/2022/05/cropped-名称未設定d.png)
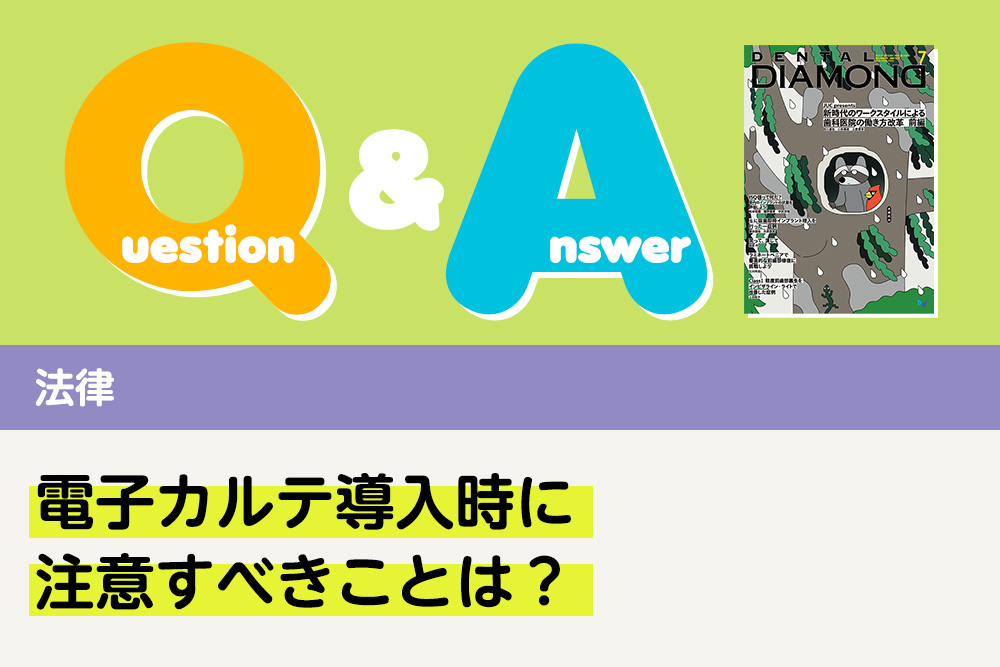

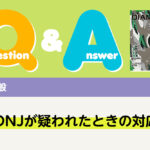


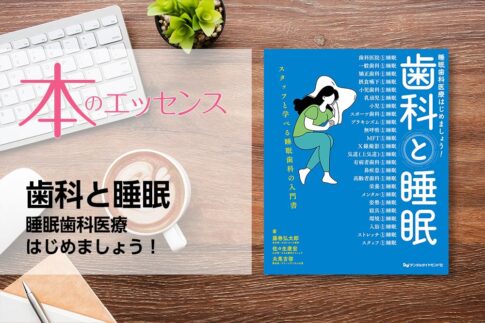
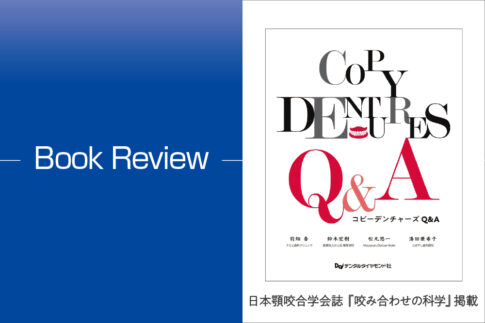
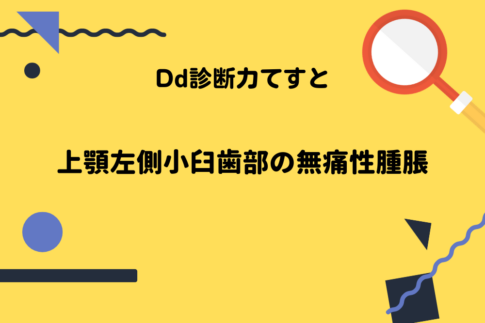
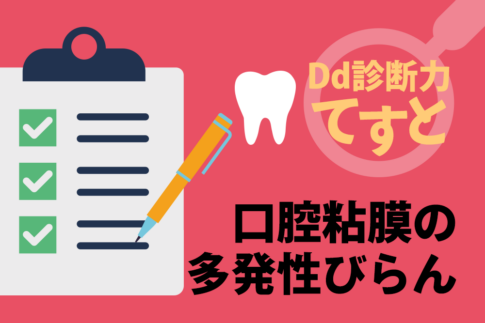

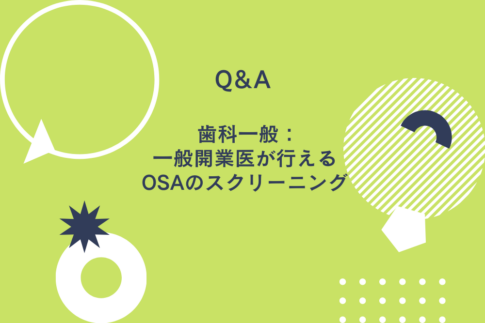



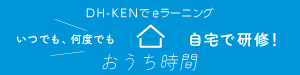
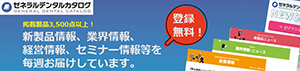


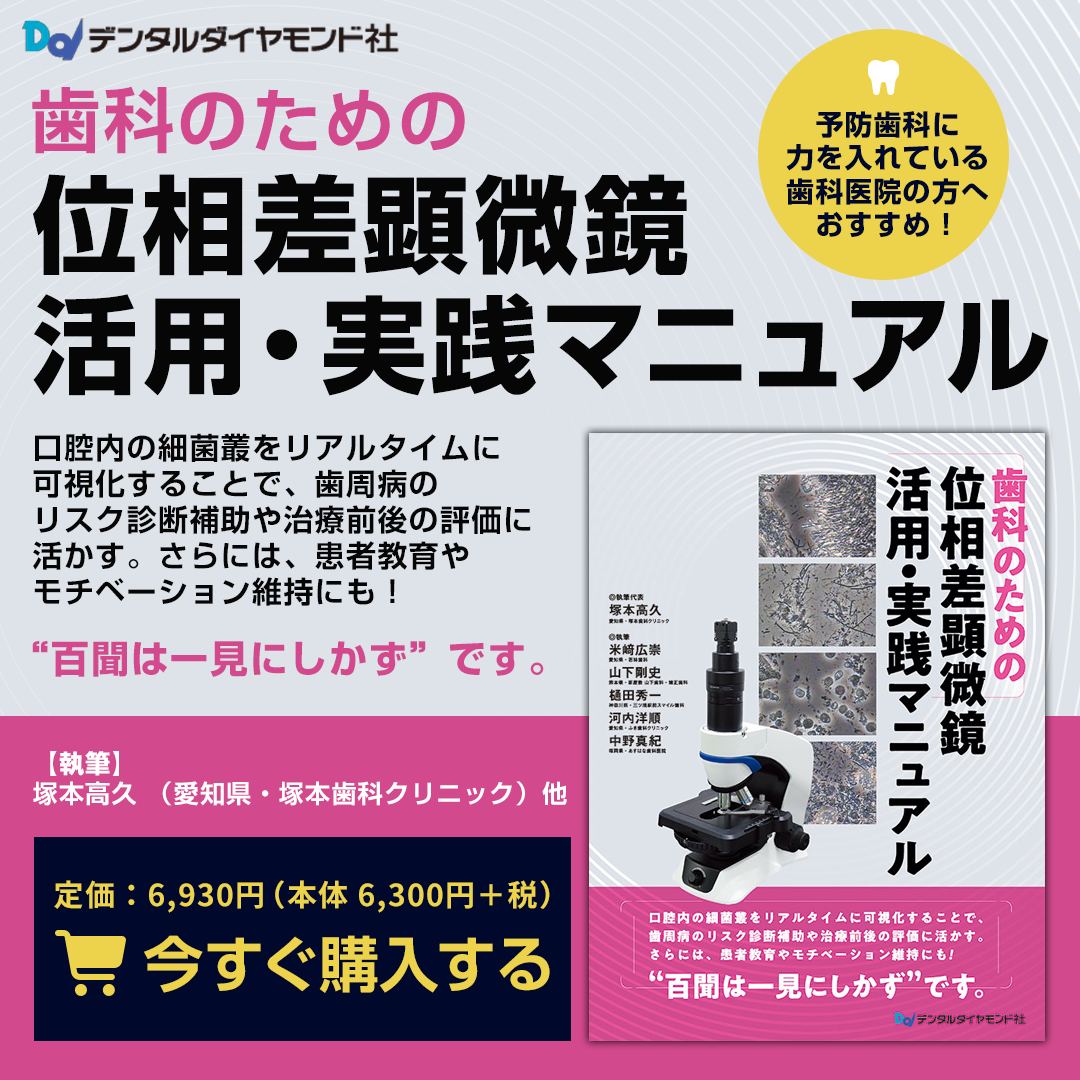
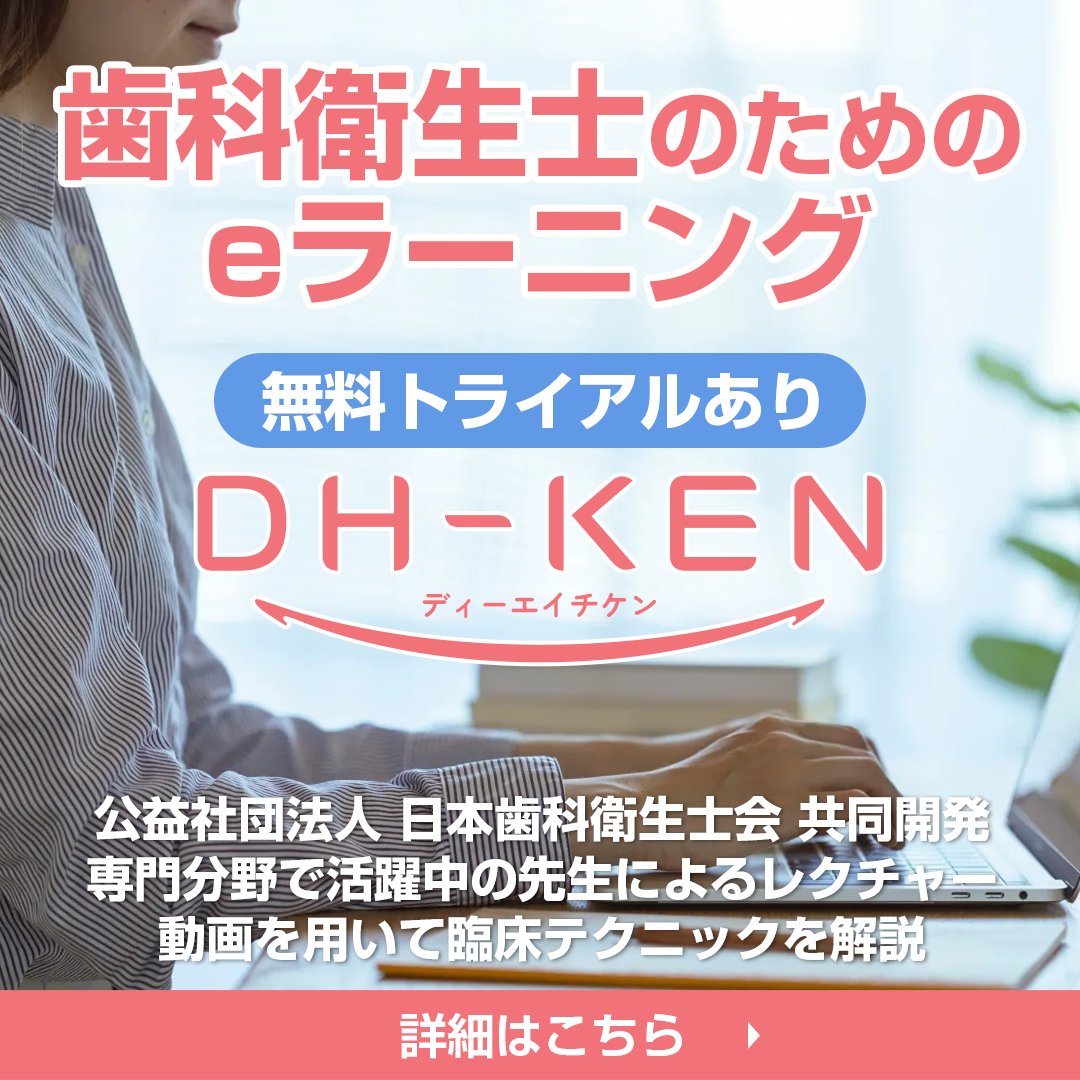

学術・経営・税務・法律など歯科医院での治療・経営に役立つQ&Aをご紹介いたします。今回は、月刊 デンタルダイヤモンド 2025年7月号より「電子カルテ導入時に注意すべきことは?」についてです。